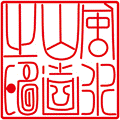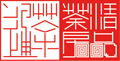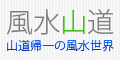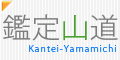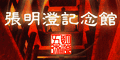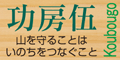『風水論考Ⅰ』
方位と空間を考える
そろそろ、「風水」をただの伝統的思考様式で終わらせてしまうのではなく、一歩進んだ科学的知見による解釈と、問題提起で、伝統と現代の融合を新シリーズ、『風水論考』で、掲載して考えて行きたい。それが、現代の科学と風水の伝統の融合して行く姿だから。そして、伝統を超えるための試行錯誤を繰り返すのが、山道帰一の『風水論考』による試みです。
風水を理気だけの家相として、趣味で終わらせるのではなく、もっと発展性のある「生きた風水」の研究には、当然、「大地」、「地質」、「大気」、「電気」、「空気」、「水」など、実に様々な地球科学や地学における研究をも考慮しなければなりません。
風水という古代自然科学で観察、もしくは考察してきたものを引き続き、現代知識を用いて、色々な諸要因を見つめ、風水を考察することが出来なければ、風水は科学的根拠の伴わないただの迷信で終わってしまうでしょう。
実際に多くの古典からの技法の大半が、現代の知識の上で、否定されつくされました。もちろん、電気傾斜にみられるような先端物理学の研究が、風水の巒頭の理想とされる等高線を描いたものと類似したりするような逆の「風水が最先端の物理学の知識を包括していた」という現象もあるのです。
現代に生きる我々が、現代知識を理解しようと努めたりすることが出来ないのならば、ある意味、現代という時代の流れについてこれていない人間ということになってしまいます(笑)。
例えば、ニュートンが出て来るまでは宇宙の運動と地上の運動は全く別のものでしたが、わずか数行で書ける簡単なルールの発見のおかげで、それらは同じものであることが実証されました。つまり、りんごと月は同じルールに従って、動いているということがわかりました。そうやって、宇宙の運動と地上の運動同じルールに従って、動いているということが実証され、現代の知識になったのです。
同じく、 超弦理論で、目指されているのは色々な力の統一です。今の我々は「電気の力は磁気を生み出し、磁気の力は電気を生み出す」、ということを知っています(モーターや発電機)。そういう意味では、電気と磁気は同じものの別の面に過ぎないわけですが、ちょっと前までそんなことはちっとも当り前のことでは無かったのです。
物理学の進歩によって、磁気と電気と言う別のことを一つの「ルール」で書けるようになりました。原子、素粒子、クォークといった微小な物のさらにその先の世界を説明する理論の候補として、世界の先端物理学で最も活発に研究されている超弦理論の研究は、色々な力の統一を実証して行く可能性もあります。
同じく、風水という自然科学を考える上でも、現代において様々な角度で実証された知識は、風水を読み解く上で、一つの「ルール」となりつつあります。
そのため、研究心と向上心溢れる風水研究をするものたちに、各自考えてもらいたいコーナーが、『風水論考』です。風水を趣味で終わらせるだけでは、満足できずに、もっと、風水を研究してみたいと熱望する人たちに突きつける「風水の命題」から考えるコーナー『風水論考』です。
ここでは、私の見解というものを極力省きました。というのも、私の見解を置けば、それが一つの定義となり、読者が考えるという作業を省き、風水上の理論として使用されてしまうドグマ性を持つからです。そのため、私が一つ一つの自然科学における要因を取り上げ、研究発表する機会は、別の発表の場で行ないたいと考えております。ここで取り上げた一つ一つの事象は、私が見つめている風水の命題と関係性を持つものと考えていただければ幸いです。
そのため、このコーナーでは、現代知識をきっかけに、読者自身が、風水に及ぼすであろう影響を一つ一つの成り立ちから考え配慮していただければ幸いです。それは、この大自然との接し方であり、大自然をどう観察するかという自然科学の命題です。
当然、過去に風水は、「この大自然から如何にエネルギーを導き出すか。」を時代ごとの最新の研究や天体観測の新しい知識を次々に取り込み、考え続けてきました。つまり、最新の研究と知識をおろそかにするということは、発展を止めるということなのです。風水を発展させるために、我々に与えられた課題は、古人のそれと同じだと言わざるを得ません。そして、風水の発展は、今後も続いて行くのです。
何故ならば、風水は、博物館の展示品でもなければ、懐古趣味でもなく、生きた知恵だからです。そして、風水は人の知恵と共に発達してきました。
第一回では、「方位と空間を考える」というテーマに従い、「方位とは何か?」、「空間とは何か?」を現代知識と共に、考えていければ幸いです。それぞれの要因や影響を与えるものを考える動機になるように、簡潔に説明を加えています。
<方位>
地球は自転し、宇宙から地球を見つめれば一つとして同じ方位などなく、人間が磁石の北方を指す極である磁極を指して、方位と称しているだけである。方位は、あくまでも、地球上に棲息する人間が、地球から見るか、宇宙から地球を見るかによって方位は成り立たなくなる。方位は基準となるものがあって成り立つ。
<空間>
地表から大気に覆われている位置までを空間と定義するのならば、自転によって、大気自体の変化も考慮しなければならないだろう。大気の中でも、特に地球の地表付近のものを空気と呼んでいる。
以下の二つの大気に影響を与えるものを考慮しなければ空間を定義できない。
① 惑星間引力と磁場の考慮
大気圏は高度500kmを超える範囲まで広がっている。そして、宇宙空間との境界は便宜的に高度80kmから120kmあたりとされている。そのため、人間が地球上から、大気、とりわけ空気を含んだ空間と言うものを考えるにあたって、既に宇宙と隣接していることからも、大気を形成する磁場が空間を形成していることになる。そのため、宇宙からの惑星間引力によって引き起こされる諸々の磁場を形成する影響を考慮しなければならない。
② 地球の自転
地球を宇宙から見た場合、地球が自転によって、動いており、空間といわれる人間の意識によって定義づけた意識世界とは別に、実際に地球が360度一回自転し、所要時間として約23時間56分4.06秒かかっている。つまり、同じ景色、同じ場所だと思われていた意識における空間は、厳密には一秒ごとに変化しているのである。
以下、考慮されるべき、方位や空間の成り立ちに影響を与える諸要因たちである。簡潔にまとめてあるが、一つ一つ概念として理解して、風水に臨まなければならない。地学、地球科学の知識は、風水を現代知識から読み解く上で必須と言える。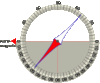
【磁極】
(magnetic pole)
(1) 磁石の両端の、鉄を吸引する力の最も強い点。一つの棒状磁石を水平に吊したとき、北を指す方の磁極をN(北、正)極、他端の磁極をS(南、負)極という。同種の極同士は斥けあい、異種の極同士は引きあう。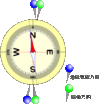 (2) 地球上で磁針の伏角が90度になる地点。北にあるものを北(磁)極、南にあるものを南(磁)極という。国際標準地球磁場 (IGRF-10)による、 2005年の京都 (北緯35.0度、東経135.8度) での磁石の針の水平面内の向き (偏角) と地磁気極と磁極の方向 (左) 及び伏角 (上)。 EWSNがそれぞれ地理的な東西南北の方向を示している。
(2) 地球上で磁針の伏角が90度になる地点。北にあるものを北(磁)極、南にあるものを南(磁)極という。国際標準地球磁場 (IGRF-10)による、 2005年の京都 (北緯35.0度、東経135.8度) での磁石の針の水平面内の向き (偏角) と地磁気極と磁極の方向 (左) 及び伏角 (上)。 EWSNがそれぞれ地理的な東西南北の方向を示している。
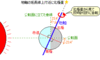 【地球の自転と公転】
【地球の自転と公転】
地球が一回自転する間に地球はさらに同じ方向に太陽の周りを公転しているので、自転周期は1日(24時間)よりも236秒短くなる。いいかえれば、地球が1回転してなお昨日の太陽と同じ向きになるには、もう236秒必要とする。
【双極子磁場】
地磁気は、地球の液体核内の対流運動が引き起こす電磁誘導がその源であるが、やはり対流運動がコリオリの力を強く受けるため、結果として自転軸方向にそろった双極子磁場が生成される。![]()
 【コリオリの力】
【コリオリの力】
コリオリの力(コリオリのちから、Coriolis force)は、回転座標系(Rotating reference frame)上で移動した際に移動方向と垂直な方向に移動速度に比例した大きさで受ける慣性力の一種。コリオリ力、転向力(てんこうりょく)ともいう。1835年にフランスの科学者ガスパール=ギュスターヴ・コリオリが導いた。回転座標系における慣性力には、他に、回転の中心から外に向かって働く遠心力がある。
地球は自転しているため、北極点上空から見ると反時計回り、南極点上空から見ると時計回りに回っている。そのため、北半球では右向き、南半球では左向きのコリオリの力が働く。地球が(ほぼ)球体のため、その大きさは緯度によって異なる。そのため、大砲やロケットなどの弾道計算にはコリオリの力による補正が必要である。
【大気電磁現象】
●オーロラ 太陽に端を発する「太陽風」と呼ばれるプラズマ粒子の流れが地球磁場と相互作用し、複雑な浸入過程を経て地球磁気圏内の夜側に広がる「プラズマシート」と呼ばれる領域にたまる。プラズマシート中のプラズマ粒子が地球大気(電離層)に向かって高速で降下し、大気中の粒子と衝突すると、大気粒子が一旦励起状態になり、それが元の状態に戻るときに発光する。これがオーロラの光である(発光の原理自体は蛍光灯と同じ)。
太陽に端を発する「太陽風」と呼ばれるプラズマ粒子の流れが地球磁場と相互作用し、複雑な浸入過程を経て地球磁気圏内の夜側に広がる「プラズマシート」と呼ばれる領域にたまる。プラズマシート中のプラズマ粒子が地球大気(電離層)に向かって高速で降下し、大気中の粒子と衝突すると、大気粒子が一旦励起状態になり、それが元の状態に戻るときに発光する。これがオーロラの光である(発光の原理自体は蛍光灯と同じ)。
●火山雷
火山雷(かざんらい、volcanic thunder)とは、火山によってもたらされる雷のことである。この雷は、火山という条件上とても近づきにくい条件で発生するため、詳しい諸量の観測はしにくい。
火山が噴き上げる水蒸気、火山灰、火山岩などの摩擦電気により生じる。また、水蒸気が少ない場合でも発生できる。しかしながら流動性の高い高温なパホイホイ溶岩などの溶岩を吹き上げる火山の場合は、高温な溶岩が電気を通しやすい性質上、雷はほとんど発生しない。また、火山灰、火山岩などの固体による摩擦電気がもたらす雷であるので、通常の雷よりも静電エネルギー量は一般的に高いとされている。
●雷 地表で大気が暖められることなどにより発生した上昇気流は、湿度が高いほど低層から飽和水蒸気量を超えて水蒸気が発生して雲となり、気流の規模が大きいほど高空にかけて発達する。
地表で大気が暖められることなどにより発生した上昇気流は、湿度が高いほど低層から飽和水蒸気量を超えて水蒸気が発生して雲となり、気流の規模が大きいほど高空にかけて発達する。
この水蒸気は高空に達すると氷結して水滴やあられ、氷の結晶となり、上昇気流にあおられながら互いに激しくぶつかり合って摩擦されたり砕けたりすることで、静電気が生じる。この時、雲の上層には正の電荷が蓄積され、下層には負の電荷が蓄積される。
急激な上昇気流により低層から高空まで形成される雷雲は主に積乱雲などで構成され、熱雷(俗に夏雷)と呼ばれる。
同じ積乱雲でも寒冷前線上などに発生する場合、また温暖前線などで同様のメカニズムが発生した場合の雷は、界雷と呼ばれる。
上昇気流が台風などによる場合は、渦雷(うずらい)と呼ばれる。
●太陽嵐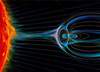 太陽嵐(たいようあらし, 英:Solar storm)とは、太陽で非常に大規模な太陽フレアが発生した際、爆発的に放出される太陽風・電磁波・粒子・粒子線などが、地球上に甚大な被害をもたらす現象である。
太陽嵐(たいようあらし, 英:Solar storm)とは、太陽で非常に大規模な太陽フレアが発生した際、爆発的に放出される太陽風・電磁波・粒子・粒子線などが、地球上に甚大な被害をもたらす現象である。
太陽は、電気を帯びたガスを放出しており、これは太陽風と呼ばれている。通常は地球の周りにある磁気圏が太陽風を地球に直接当たらないように逸らしているが、時々これが極地域に流れ込むことがある。このとき、オーロラ、磁気嵐、デリンジャー現象などの電磁的な現象が起こる。太陽活動には、太陽の自転周期である約28日、太陽黒点数の変化周期である約11年、約200~300年の3つの周期がある。11年周期の活動を繰り返すうち、11年に1回、活動がもっとも活発な極大期を迎える。
極大期には、人工衛星や電子機器などに被害をもたらすような強い太陽風が発生することがある。また、強力な太陽風が発生した場合も、磁気圏を破って地球に到達することがあり、特に強い場合は被害をもたらすことがある。歴史上最も激しい太陽風は2003年11月4日のもので、人工衛星や惑星探査機に影響が及び、国際宇宙ステーションでも念のため避難が行われた。しかし、被害は限定的で一時的なものであった。
この史上最大の太陽風はX28(フレア参照)であったが、これをはるかに凌ぐ歴史的な規模の太陽風が発生する可能性が指摘されている。とくに、人工衛星や電子機器の普及が進み、太陽活動に関する研究が発展した近年、この太陽風によって地上に大きな影響がもたらされることも考えられるようになり、「太陽嵐」と呼ばれている。
●過去の太陽嵐
過去に発生したと推定されている太陽嵐は以下のとおり。
1805年
1859年
非常に激しいCMEが発生、18時間足らずで地球に到達し現在でも史上最大とされる規模の磁気嵐を発生させた。まだ普及途中であった電信機器は回路がショートし火災が発生した。
1958年
激しい太陽フレアとCMEが発生。アラスカのフェアバンクスでは非常に明るいオーロラが観測され、メキシコでも3度に渡ってオーロラが観測された。
●中間圏発光現象
中間圏発光現象(ちゅうかんけんはっこうげんしょう)とは、高度50-80kmに広がる中間圏に起こる発光現象を言う。中間圏は大気密度が非常に低く、対流も少ないため、気象現象はほとんど発生しないとされていた。
ところが、1989年に雷雲(高度10km以下)の上で発光現象が起こることが観測された。発光時間は1秒以下であり、数m秒から0.5秒程度である。下記のようないくつかの種類が存在する。
●レッドスプライト![]() レッドスプライトとは、雷雲上の中間圏で起こる発光現象であり、単に「スプライト」とも呼ばれる(以下「スプライト」と書く)。中間圏発光現象の1つである。
レッドスプライトとは、雷雲上の中間圏で起こる発光現象であり、単に「スプライト」とも呼ばれる(以下「スプライト」と書く)。中間圏発光現象の1つである。
雷とは全く別の発光現象ではあるが、雷(雷放電)に付随して発光するといわれている。
近年衛星(ROCSAT-2衛星搭載のISUAL観測器等)からの観測も行われている。
【大気圏】 大気圏(たいきけん)とは、天体などの巨大な物質を取り囲んでいる気体の層の総称。これら気体は、物質の重力によって引きつけられている。重力が十分で、かつ気体の温度が低ければ低いほど引きつける力は強くなる。
大気圏(たいきけん)とは、天体などの巨大な物質を取り囲んでいる気体の層の総称。これら気体は、物質の重力によって引きつけられている。重力が十分で、かつ気体の温度が低ければ低いほど引きつける力は強くなる。
惑星という観点から見ると、大気は地質学者が惑星が惑星の形態をなすまでの作用を考える上で重要なものである。
風は、ちりや粒子など、土地の起伏を浸食し堆積物を残す(風成システムとも呼ばれる)。霜や降水も、起伏に左右される。気候変動は、惑星の地史に影響を及ぼしうる。逆に言えば、地球の表面についての研究は、惑星の大気圏・気候の現在、過去両方の理解をもたらす。気象学者にとって、大気圏の構成は気候とその変化を決定するものであり、生物学者にとっては、大気圏の構成は生物の発現や進化と密接に関連しているものなのだ。
【地球の大気】 地球の大気(ちきゅうのたいき)または地球の大気圏(ちきゅうのたいきけん)は、地球の万有引力によって保たれている気体の層である。大気圏は高度500kmを超える範囲まで広がっている。ただし、宇宙空間との境界は便宜的に高度80kmから120kmあたりとされている。
地球の大気(ちきゅうのたいき)または地球の大気圏(ちきゅうのたいきけん)は、地球の万有引力によって保たれている気体の層である。大気圏は高度500kmを超える範囲まで広がっている。ただし、宇宙空間との境界は便宜的に高度80kmから120kmあたりとされている。
地球科学で大気圏とは、地球環境を大気圏、水圏、陸圏(地圏, 岩石圏)、生物圏に区分したうちのひとつ、という位置づけである。
大気の中でも、特に地球の地表付近のものを空気と呼んでいる。
●地球大気の鉛直構造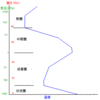 地球大気は鉛直方向に温度変化が激しいため、温度変化を基準に四つの層に区分されている。これを「地球大気の鉛直構造」という。
地球大気は鉛直方向に温度変化が激しいため、温度変化を基準に四つの層に区分されている。これを「地球大気の鉛直構造」という。
●対流圏
0-9/17km。高度とともに気温が低下。さまざまな気象現象が起こる。赤道付近では厚く、極では薄い。成層圏との境界は対流圏界面と呼ぶ。
●成層圏 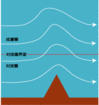 9/17-50km。高度とともに気温が上昇。オゾン層が存在する。中間圏との境界は成層圏界面と呼ぶ。
9/17-50km。高度とともに気温が上昇。オゾン層が存在する。中間圏との境界は成層圏界面と呼ぶ。
中間圏
50-80km。高度とともに気温が低下。熱圏との境界は中間圏界面と呼ぶ。
熱圏
80-800km。高度とともに気温が上昇。
成層圏と中間圏をあわせて中層大気とも呼ぶ。熱圏のさらに上部に外気圏をおく場合もある。
【地磁気】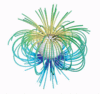 地磁気(ちじき)は、地球が持つ磁気及びそれにより地球上に生じる磁場の総称。 ベクトル量であり、大きさと方向を持つ。大きさの単位には通常「nT(ナノテスラ)」が用いられる。
地磁気(ちじき)は、地球が持つ磁気及びそれにより地球上に生じる磁場の総称。 ベクトル量であり、大きさと方向を持つ。大きさの単位には通常「nT(ナノテスラ)」が用いられる。
地球の磁場は、概ね磁気双極子で近似でき(つまり、地球の中心に仮想的に置かれた一つの小さな強い棒磁石だけによって作られていると見なせる)、現在は北極部にS極、南極部にN極に相当する磁極がある。地球の双極子磁場は自転軸に対して約 10.2 度(2006年)傾いているため、地理上の極と磁極の位置にはずれがある。
●特徴
地磁気のベクトルは、赤道付近を除けば、地面に対して平行ではなく、地面と斜めに交わるかたちになっている。ある地点において水平面と地磁気のベクトルとがなす角を伏角といい、地磁気が地面に向かって突き刺さる方向の場合がプラス、地面から出て行く向きの場合がマイナスとなるように定義される。伏角は、南半球のほとんどでマイナスで、南の磁極に近づくにしたがって -90 度に近づく。また、北半球のほとんどでプラスとなり、北の磁極に近づくにしたがって +90 度に近づく。ただし、地球磁場は双極子磁場とは完全には一致しないため、伏角が -90 度あるいは +90 度になる点は、地球双極子磁場の極とは一致しない。
一方、地磁気のベクトルを水平面に投影したときに、地理上の真北となす角は偏角と呼ばれる。偏角が現れるもっとも大きい要因は、地球の双極子磁場が自転軸に対して傾いていることである。しかし、やはり地球磁場が双極子磁場と完全には一致していないことから、偏角も双極子磁場の極の方向とは一致せず、伏角 +90 度の点の方向にもならない。例えば日本の場合、双極子の北極は、日本から見ると地理上の北極より少し東の方向になるが、偏角はやや西を向いている。
●発生原因
地表で観測される磁場は、その大部分が、地球のコアに流れる電流に起因する。コアは金属鉄を主成分としており、電気伝導度が比較的高い。コアに一様に電流が流れると仮定すると、地磁気の双極子モーメントから予想される電流の強さは数 10億 アンペアにも達する。ただしコアは半径が 3,500 キロメートル弱と、地球半径の半分以上も占めており、きわめて巨大であるため、電流密度にすれば 1 平方メートルあたり数ミリアンペア程度である。
その他の原因としては、地殻が磁化していること、電離層に流れる電流、地殻やマントル、海水などに流れる電流、などがあげられるが、これらの寄与は一般には小さい。なお地球の深部は高温のため、鉄を含め、多くの強磁性鉱物はキュリー点を越えてしまい磁化を失う。したがって強く磁化しているのは地球のごく表層だけである。地球は大きな電磁石であるといえる。
●地磁気の強さ
地磁気の強さは場所によって異なり、磁力は 24,000 - 66,000 nT(0.24 - 0.66 ガウス)。赤道では弱く、高緯度地域では強い。東京付近は約45,000nTである[1]。
●変動
地磁気は、常に一定ではなく、絶え間なく変化している。磁気嵐や、激しいオーロラが発生したときには、数秒から数日のスケールで激しく変化する。このような現象は、太陽風と関係がある。
磁気嵐やオーロラがない場合でも、一日周期で数 10 nT 程度の変化が見られる。このような一日周期の変化を「日変化」と呼ぶ。日変化は太陽放射と関係がある。
以上は、地球外部の要因による変化であるが、地球の発生する磁場そのものがさまざまな時間スケールで変化していることも知られている。このうちもっとも劇的な変動は地磁気の逆転であろう。これは地磁気極の N 極と S 極が反転する現象で、古い火山岩などがもつ磁化を測定することで、過去の地磁気の様子を推定するという古地磁気学によって明らかにされた。地磁気は平均すると 100 万年に 1.5 回の割合で逆転を繰り返しているが、その割合はかなり不規則である。たとえば白亜紀には1千万年以上にわたり逆転のない期間があったと推定されている。
逆転よりももう少し変動の振幅が小さい、数年から数千年程度の時間スケールの磁場変動のことを「永年変化」と呼ぶ。地磁気は年々弱くなっており、ここ 100 年では約 6% 弱くなった。これはあと 1,000 年足らずで地磁気が消滅してしまうほどの減少率であるが、この程度の磁場変動は過去においてもそれほど珍しいものではない。
【ダイナモ作用】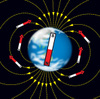 コアに流れる電流は、エネルギーの入力が何もなければ、電気抵抗のために減衰し、10 万年程度で消えうせてしまう。コアの電流を維持するしくみを、地球のダイナモ作用という。
コアに流れる電流は、エネルギーの入力が何もなければ、電気抵抗のために減衰し、10 万年程度で消えうせてしまう。コアの電流を維持するしくみを、地球のダイナモ作用という。
地磁気を維持している根本の原因のひとつは、コアの冷却である。地球が誕生したときには、コアは溶融しており、液体の状態にあったと考えられる。現在も、地震波の伝わり方の特徴から、コアの大部分は液体状態のままであることがわかっている(一部固化して内核を形成している)。コアの表面の温度が下がると、熱収縮により密度が上昇し、コアの内部に沈み込もうとする。一方内部の熱い液体は上昇し、熱をマントルに捨てる。これがコアの熱対流運動である。
熱対流によって生じる運動エネルギーは、通常の発電機(ダイナモ)と同様、電磁誘導の原理によって、電磁気的なエネルギーに変換される。その過程は次のようにまとめられる。
コアに初期電流が流れる。
電流は周囲に磁場をつくる。
その磁場中で、液体鉄が熱対流運動し、誘導起電力を生じしめる。
その起電力により、電流が流れる。
4の電流が初期電流を強めるならば、電流は指数関数的に増大する。ただし磁場中を電流が流れるとローレンツ力が発生し、それは熱対流を妨げる向きにはたらくので、電流と流速とは適当なバランスのもと、ある大きさに保たれる。
通常の発電機では、永久磁石がつくる静磁場をもとにして起電力を得ている。しかしコアの場合、自分自身に流れる電流のつくる磁場を用いて誘導起電力を得ている点が、きわめて特殊である。このような発電のしくみを自励ダイナモという。コアのダイナモ作用は熱力学および電磁流体力学によっておおむね記述できる。しかしこれは非線形過程であり、数学的に解析するのは容易ではない。そこで計算機をもちいた数値シミュレーションが1980年代から行われるようになった。とくに1990年代後半に至って、地球に近い環境下で、自発的に磁場が生成されうることが確認された。生成される磁場が自転軸に沿った双極子磁場で表されることや、逆転を含めた時間変動の特徴なども再現されている。
●地磁気の利用
地磁気の利用は古くから行われており、方位磁針を用いて方位を知るために用いられてきた(この場合得られるのは磁気方位であり、地理上の方位を得るためには磁気偏角で補正しなければならない)。また、伏角を利用して姿勢計測・制御を行うようなシステムも存在する。また、地磁気を利用したモーションコントロールセンサーも携帯電話等に実装例がある。渡り鳥や回遊性の海生動物の中には地磁気を方位を知る手段として利用しているものがある。