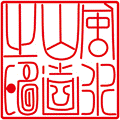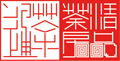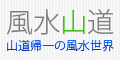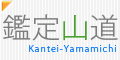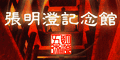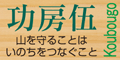風水において理気と呼ばれる「時間による気の運行の循環による作用」とは、何かを考察してみたい。
文献学的に「理気」という言葉、古典籍から調査するに際して、「理気」という単語は、程兄弟によって整理された「太極図説」から南宋の朱子(1130年 - 1200年)によって整理された「理気二元論」に初めて見出すことができます。そして、この「理気二元論」が、現代にまで伝わる風水の「理気」理論のベースになっていると考えられます。と言いますのも、それ以前に「理気」と呼ばれる概念を風水古典籍から見出すのが困難なためです。
南宋の朱熹は張載(1020年-1077年)の気と程頤(1033年-1107年)・程顥(1032年‐1085年)の理を融合して理気二元論を唱えました。世界にアプリオリに存在し、気の集合離散を秩序づける法則・理法を理と呼び、理先気後を主張しました。朱熹は、人間の死を気の離散とし、いったん離散した気は元に戻らないと考えたのです。しかし、弟子に「では、祖先祭祀はどうして行うのか」と問い質され、これは朱子学の重大な理論上の欠陥となったとされます。
*アプリオリ-「私はこのことを知っているが、経験を通じて知ったのではない」という言葉に表れてくる意味合いです。
明代中期になると理先気後に対して理気相即が唱えられるようになり、理は気の条理(いわばイデアではなく形相)とされるようになりました。このように理気論は気一元論へと収束されていきました。そして、清の戴震(1724年-1777年)にいたっては理は気によって生じるアポステリオリなものとされるに至ったのです。
*アポステリオリ-アプリオリの対語だが、経験を通じて得られる知識は、総じて100%確実な知識とはみなされない。
なので、哲学者の中にはアポステリオリな知識をアプリオリな知識より格下と位置づける者もいます。
この理と気が結びついて万物が存在するという二元的存在論に基づいて、これを人間の道徳に応用し「性即理」と呼ばれる「心の本体である性は理であるから、気(欲望)を捨てて理にしたがって生きる」ことを理想とする倫理説が説かれました。
ちなみに、その学問方法として「格物致知」と言われる「物の理をきわめて、知をつくすこと」が提唱されました。それは、従来儒教の聖典とされてきた「五経」よりも「四書」(大学・中庸・論語・孟子)を重んじた結果でもあります。
つまり、風水における理氣とは、南宋の朱子によって、思想的な始まりとするというのが、正しい歴史におけるあり方です。儒教の流れを汲む朱子学「理気二元論」の思想の展開と共に理氣説は風水にも融合し、それは一つの思想が人々の意識に投影された姿そのものなのです。
風水における「理氣」とは、「理氣二元論」を思想的母体とし、少なくとも、南宋の朱子が提唱した「理先気後」と明代中期には「理気相即」と変遷し、清の戴震に至って「気一元論」へと集約され、少なくとも、三段階の変遷を遂げました。
そして、理氣説の思想潮流は、風水にも反映され、少なくとも、風水における理氣は上記の変遷と同じく、三段階に分かれて、組み上げられた事が伺われるのです。
つまり、この三種類の理気に対する思想は、まったく別の理氣であると言えるでしょう。こういった時代や思想背景を考慮して、時代ごとの風水を見直さなくてはならないところに、風水を論じる怖さがあります。つまり、それは風水の解釈にも反映され、時代ごとの哲学思想を読み解かなければ風水は絶対に理解できないのです。
ちなみに、この辺りが日本ではまったく理解されていないように思えてなりません。
要約すれば、「理氣」とは、朱熹によって唱えられ、「理気説(理気二元論)」とは、「宇宙・万物は、理と気からなる。理は人・物の性(本性・本質)であり、気は物質・存在を意味し、この理と気が結びついて万物が存在する」という二元的存在論を意味します。
そして、南宋の朱子が提唱した「理先気後」と明代中期には「理気相即」と変貌し、清の戴震に至って「気一元論」となり、それぞれの時代背景ごとに、思想として読み解かれた「理氣」のあり方は様相を変え、そして、それぞれの時代に反映され、それは風水も例外ではないということです。
古代ギリシアの哲学者であるプラトン(紀元前427年 - 紀元前347年))の提唱した世界観であるイデア論は、個別の事物の背後には、その本質であるイデア (Idea) が実在すると主張する哲学でした。
プラトンのイデア論は、「理」による朱子哲学と還元でき、そのイデアに対する「気」という物質や存在についても言及し、気一元論理に至っては、気の条理がイデアではなく形相とされるようになりました。
参考として、気一元論において風水の「理氣と巒頭」という区分を考えるのならば、理氣と巒頭という関係は矛盾するものとなります。と言いますのも、気一元論における「気」は既に形相にまで言及しており、全てを気で読み解こうとしている世界観だからです。そこに巒頭という区分があること自体が矛盾することになるのです。
つまり、現代における様々な風水に見られる「理氣と巒頭」という分類法の「理氣」は、清の戴震に至って収束された気一元論という見解にまで言及していないと考えるべきです。ちなみに、小生は、「風水とは」で書きましたが、気一元論による風水の世界観をアポステリオリの立場で考察しております。
理氣説は、実に様々な二つの「理」と「気」をめぐり、交錯する世界観そのものが時代ごとに人々の意識に反映されつづけたのです。
つまり、風水で使われる「理氣」という言葉の背景をも考慮するのならば、哲学の命題である「本質(理)」と「存在(気)」をどう読み解くことが出来るかが、本当の意味での風水の理氣を読み解くことなのではないでしょうか。
そのため、理氣説の変遷と同じく、風水における理氣説も、様々な流派によって解釈が異なり、その相違は、時間に対する概念、存在に対する定義、本質に対するアプローチと、実に様々な点において違いが見られますが、哲学における見解の相違という点を考慮するのならば、それは至極当然のことだったと言えるでしょう。
風水を考えた流派(学派)の持つ、「本質」、「存在」に対する哲学的見解の相違が、即ち、風水で言う「理氣」の違いを生み出し、様々な学派(流派)が生まれたのです。そして、それは完全に流派と呼ばれた学派の持つ哲学的洞察が反映されたものでした。
つまり、風水において「理氣」を見るということは、二元的存在論について人、物の本質を存在と結び付けて考える哲学上のパースペクティブそのものであると言うことです。
*パースペクティブ―ものの考え方、或いは全体的な視野という意味。