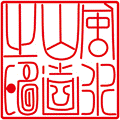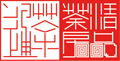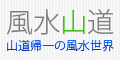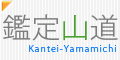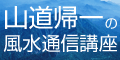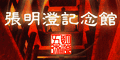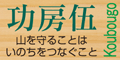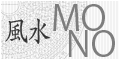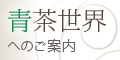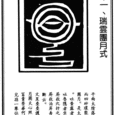春に開催され、半年を経て本年度二回目となる入門講座、そして三回目となる基礎講座が9月22・23日に開催されました。
今回はもう怜香先生にすべて任せて、後ろでおとなしゅうして見ているはずだった・・・のに。(笑) 入門講座の翌日の基礎講座では、「後ろからうるさい!前に行け!」とスタッフから忌憚なき意見をいただきまして。(*´ε` *)
怜香先生講座に基礎から参戦! やっぱり、後ろからの景色と前から臨むのとでは違うなあと感じ入りながらも、縦長の教室で、後ろの席の人がホワイトボードの文字が見えるかな~っと心配になって、「このCは、左右どっち?」とか、一番後ろの人に視力テストしてみたが全く意味が無かったな。(笑)
本だと紙面に制限やページ数に限りがある。しかし講義ではそういったリミッターを外し、出せる、魅せる、鑑定実例の量は『玄空飛星派風水大全』所収の量とは比較にはならないほど多い。また、鑑定実例を通じて学ぶというのは参加者の認識を大いに助けることだろう。
今回の講座で目指したのは、再受講者たちに更なる発展と学びがあるようにすることだった。そのため、事前に怜香先生ともいろいろ打合せし、用意した鑑定実例集となるパワーポイント資料は100ページちかくあるため、当日に検索で素早くヒットする用語を入れておいたりと、色々と工夫して前回と今回とでは使用する実例の大半を変えて、講義に臨みました。
しかし、そんな講義前の工夫や仕込みが一切通用しないのが、生の授業と言うもので、講義を受ける受講生たちは、まるで海のごときものである。海が凪いでいるときもあれば、荒波となることもある。今回は入門講座から怒涛の波となって質問は後を絶たなかった。素晴らしい波だ!だが、参加者が想定を超えて多かったため、一人で次々とくる荒波を乗りこなせず、怜香先生が涙を流さないようにと、次の日の基礎講座から山道帰一投入で。(笑)
そう、講義のカリキュラムはガイドラインとして決まっているが、その内容や質は参加者たちによって左右されるのは言うまでもない。非常に面白味のある入門講座で後ろからアンサーしているのは、もはや疲れた。この波を全力で乗りこなしたい!自分が楽しめない講義は、参加者にとっても楽しいはずがないのだから。
参加者たちの織り成す波と講師が一体になる講義が一番充実していて楽しい。生徒が悪さして破門するのは嫌だが、参加者たちが発する熱意ある質問という波紋は講師としては嬉しいことです。
学んでいるから出てくるであろう質問が多く、講義に一連の流れとドラマやトラウマがあった。(笑) そんな入門講座、基礎講座になったと思います。テキストも大幅に変更し、結果的に講義内容も半年前の基礎講座とは全く異なった展開や資料や鑑定実例の説明となりましたね。
また、皆さんのご参加をお待ちしています!入門講座、基礎講座で、海が凪いでいるときは後ろに黙って座っています。でも、荒波が来たら、乗りに行きます!
今回から初公開講義となった応用Ⅱ「孔氏玄空学」は、300ページ近い私の訳註入りテキストをご用意しました。「沈氏玄空学」との比較から相違を孔氏玄空学心得として、まとめながら講義していきました。
それでは、次回10月の講座でお会いいたしましょう!