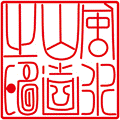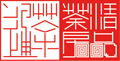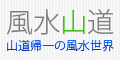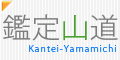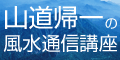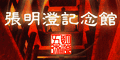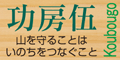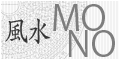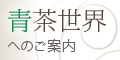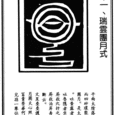以下の文章、去年の8月24日の引越し前にアップしたものなんですけれど、引越しも終わったし、結構エンジョイしてくれた研究者の方がたくさんいたようなので、研究者の研究を踏まえて、さらに彼ら彼女らががんばって調べた研究に対して返答を書き加えたものをもう一度アップしますね。エンジョイ!(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
ダニエルのコレクションのなかには、風水の定義となった唐代、郭璞の『葬書』よりも、古いとされる書物など、風水の定義自体を変えてしまうものも沢山ある。それらの貴重な歴史資料たちは、既に台湾や中国からも失われてしまった。もちろん、図書館にもない。縁あって小生が保管しているが、正しく世に出して研究したいとも思っている。
「気乗風則散、界水則止、古人聚之使不散、行使有止、故謂之風
(気は風に乗ずれば散じ、水に界てられれば即ち止まる。
古人はこれを聚めて散ぜしめず、 これを行いて止めるあり。
ゆえに、これを風水という。)」
有名な郭璞の著した『葬書』の定義も、『葬書』だけではなく、出自の古い『青烏經』『狐首經』の内容と比べると、世間で知られている最も古い定義と比較するに足る資料は沢山ある。
もう一つの、物の見方として、風水師という山野をフィールドワークする実践家の経験を踏まえるならば、『葬書』の風水定義は「気は風に乗じて則ち散じ、水に界てられれば即ち止まる(氣乘風則散,界水則止。)」とされ、日本の風水研究者の間では、この様に読み下し、「風水」を定義する。
しかし、この様な読み下しは正確な風水を論じるうえでは、水が気を遮るなどということはないので、問題があると言わざるを得ない。
私は、「気は風に乗じて則ち散じ、水に界てられれば即ち止まる(氣乘風則散,界水則止)」という解釈は、正確な風水の定義とさえいえないと思う。
「気は風に乗じて則ち散じ、水を界すれば即ち止まる(氣乘風則散,界水則止。)」ならば意味は通る。
つまり、気は水を境にして流れを止めれば気は止まるのである。当然、気脈、山脈、龍脈は水と出会い、水を境にして、その起伏を失い広大な水でできた平面と接するのである。このような、水の広がる明堂をとることを風水の専門用語で「満堂水」と言い、気が溜まり素晴らしい場所とする。
それは、学者の持つ認識ではなく、フィールドワークを繰り返す風水師たちの持つ認識の中において顕著なのである。
台湾の著名な風水師、孔日昌(1919年-1984年)は、北宋(960年-1127年)の賴文俊が著した『催官篇』の注釈書である自著の『地理催官水法』にて、「界水は来龍の止まる所であり、小祖から龍勢を下界に送ることを第一とする(界水所以止來龍,自小祖下界送龍勢者第一)」と述べている。
もし、「界水」が、「水に界てられる(水に遮られる)」ことならば、来龍の止まるところは、「水に遮られる(界水)」場所となるのだろう。しかし、それでは風水としての意味が通らない。
しかし、「界水」が、「水を界する(水を境にする)」ことならば、来龍の止まるところは、「水を境にする(界水)」場所となり、意味が通るのである。
ちなみに、明澄透派十三代の張耀文先生(1934年-2004年)は、「界水」という風水専門用語を『山龍秘旨(千金賦)』に書かれた一文を「界水が肩を穿けば、着眼を庸うこともなし(界水穿肩,無庸着眼)」と訳し、「界水」に詳細な解説を加えている。界水を「穴の範囲、雨が降れば水が通るところ」とし、「界水が穴を通れば、この穴はもう役に立たない」と説明を加えている。
つまり、「界水」とは学者が字義を追って字義の上からだけとらえるものではなく、風水師としての実践家たちが勝ち得た認識や風水学派たちの経験をこれらの専門用語に観念として加えたのは言うまでも無い。
もし、このような時宜を経た風水専門用語の解釈をできないのならば、その様な言葉尻だけの解釈など、児戯に等しい。
また、 『青囊經』、『錦囊經(葬書)』などは風水の最古の部類に属する古典籍として知られているが、『黑囊經』、『白囊經』、『黄囊經』、『紫囊經』などの五色コンプリートした古典籍の発展形態などは、あまり知られていないだろう。まあ、収集マニアにとって喜ばしいことで、こんなものを集めたから「どうだ!」とは言わないが(笑)。
日本での風水の研究は、学者を含め、あまりにも何も研究されていない。現代では、フィールドワークなどは、研究者にとって必須のテーマが、風水の分野だと思われるが、日本国内では皆無と言わざるを得ない。
また、これらの貴重な風水典籍が、民間人である小生の手元にあり、学者さんたちはあまりにも風水の大事な古典籍を持っていないのも皮肉な現状なのだろうが・・・フィールドワークくらいしても良いものだろうに。
ダニエルは、台湾や中国をフィールドワークしながら、歴史から散失した沢山の文献を自らのフィールドワークの中で、人間関係を構築し、大金を積んだり、時に譲り受けたりして手に入れた。学者さんたちは、そのような努力をしているのだろうか?もちろん、金で買えないものは、情熱で買えるようにトライするのが、ダニエルが各国を渡来して、得たものでもある(笑)。
まあ、金で買ってはならないのが、女の子の「ハート」と、価格のつけようがない心から心に伝わる「心伝」だろうと思う(笑)。ハートと「心伝」は同じですな。
狭い研究室に篭って研究しているだけでは何も生まれてこない。篭るのではなく、研究者としてフィールドワーク、尋龍点穴くらいしてみるものだろうに。もし、風水といわれる分野をまじめに研究する気がある学者さんが、日本にいるのならば。
しかし、日本で風水に携わる表の世界のプロと呼ばれる人たちが、どのくらい正しい尋龍点穴ができるか疑問が多い。
沢山本を書き、少しは「山に入ったりして、フィールドワークしているぞ!」と、自分の感性の尋龍点穴を謳う人は沢山いるが・・・伝統風水文化に裏付けられた根拠は何もない。ダニエルとある戦士が分析した日光東照宮のように。
それだけに、フィールドワークという戦場を駆け抜けた一人の戦士として風水世界を見てきたダニエルとしては、日本の風水世界といわれるプロの世界が戦場のように思えてこない。そこも、またただのぬるま湯なのだ。
そこには、ただ醜い人間関係の戦場があるだけだ。ぼくは、表側のコミュニティとどことも一切係わりがない。
何故、向上心、研究心、探究心、ありとあらゆる自分の全身全霊を賭けて、前に進み、眼前に広がる景色を見ようとしないのか。そして、学者はフィールドワークさえしないのか!?
でも、最近気づいたのは、そのような向上心と探究心がある戦士たちが、日本のプロの世界にもいるということだ。つまり、日本にも戦士、もとい武士(サムライ)たちがいて、嬉しかった。
ダニエルは、そんなプロ達を支援していきたい。チャンスがあれば、日本で台湾に隠れているある戦士などの講座も開いて見たいが、健康状態的に難しいだろう。
そもそも、現代における台湾の風水師でも大半がイカサマ師だと考えても間違いがないくらい、本場からも貴重な人材が次々に他界してしまい、風水文化の世界における職人は姿を消しています。それは、あたかも、既に高麗青磁を焼ける職人がいないように。
風水は、唐代が全盛でそれ以前の古典が風水の様々な分岐路を物語り、とても価値があるが、現代ではそこまで全く考慮されていないし、学者は唐代以前の風水文献を持ってさえいない。文献学だけが日本の学者のリサールウェポンなのに。
社会的には、研究者でもなければ、風水で生活を成り立たせているという意味でのプロではない民間人ダニエルが、日本の風水研究者達よりも、多くの文献を持ち、日々研究を重ね、何年もフィールドワークをし、多くのことを考え、古代から、現代を見つめようとしている。
そして、それが現代にとって意味のある風水思想になるように活動し始めるように流れを作るのが自分の仕事だと心得ている。
そのとき、唐代から止まった時計がもう一度動き出すように、フィールドワークだけでなく、研究も重ねたい。また、心あるプロの人たちと手を繋ぎ、現代にも価値のある風水の姿を模索したい。それは、風水から生まれる現代思想の一つになるだろう。また、そうなるように、研究をし、答えを模索している。
この文章には、せっかく学者さんが研究してくれた部分を人伝えに聞いたので、一部ライティングを加え書き直しました。
おっと、遊んでいる場合じゃなかった。(;◔ิд◔ิ) !!!
1月10日原稿の締め切りが過ぎているのである。ここで書き加えたのは、一部だけなので、本が出たら、そっち読んで下さいね。
この内容の百倍詳細で、面白く書きましたから。ただし、学術書、そして本当に伝えたい気持ちを載せた技術書として。(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
うぉぉぉぉ、もう最後の追い込みだー。図を入れたら1000ページを超えそうな勢いなんですけれど、どうしましょうか?
ただ、オレを無視してくれない、もしくはオレ無しでは生きられない熱烈な学者さんや村役場かNPOかなんだかわからない風水かどうかもよくわからないことをしている人々(学者+学者クズレの風水研究家たち)に言いたい。
ダニエル:「オレ今忙しいのよ。もうすぐ刊行予定の風水本の締め切りを
過ぎてるんだから。だから、もう少し時間ができたら、学術ゴッコしようね。
今は、あんたたちの論争に巻き込まないで、ホント、オレ今は関係ないから。
ちゃんと、参戦するから、本書かせて~。巻き込まないで~。
オレ、小休止ということでお願いします。敬具」
 ちょっと、待ってたちょうだいね。やべー漢文漬けで日本語が怪しくなっている。(;◔ิд◔ิ) !!! 去年の8月24日のこの記事の原型バージョンVer 1.0から待っていてくれたんだから、もう少し時間ちょうだいでしょ(笑)。ディベート無敗のオレが本に主義主張から理論まで色々と書いて、世間を挟んで相手しますから。待ってろよ~コイツめ~。(。´∀`)ノ゚
ちょっと、待ってたちょうだいね。やべー漢文漬けで日本語が怪しくなっている。(;◔ิд◔ิ) !!! 去年の8月24日のこの記事の原型バージョンVer 1.0から待っていてくれたんだから、もう少し時間ちょうだいでしょ(笑)。ディベート無敗のオレが本に主義主張から理論まで色々と書いて、世間を挟んで相手しますから。待ってろよ~コイツめ~。(。´∀`)ノ゚
しかし、なにはともあれ、本文の原型バージョンVer 1.0では良い仕事をした。研究不足の学者たちに火をつけてあげたんだから~。オレは「泣いた赤鬼」出てくる青鬼か!? (。´∀`)ノ゚