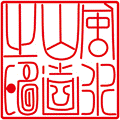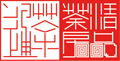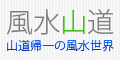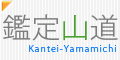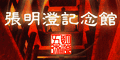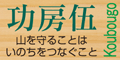天目茶碗は、自然のなせるあらゆる色彩を包括している。
天目茶碗は、自然のなせるあらゆる色彩を包括している。
江有亭(江有庭)のつくったものは、正に古典の復古だ。
歴史上無いものを作る。江有庭は、有が無に到る過程を描いているといっていた。
台湾の国宝である陶芸家「江有亭」は、化学薬品の含まない天然成分のみを使用した釉薬だけを用いて、宋代の天目茶碗を現代に復活させた。焼き上げた後、碗の縁などに何も塗らずとも、金や銀の色が自然と浮かび上がってくる。現代に残された宋代の天目茶碗は、縁を塗っているというのに。
江有亭は、東派・玉靈大仙師兄によって「江有庭」と命名される。
 江有庭の家と窯は、元中華民国総統(1988-2000)である李登輝の生まれた実家(今もちょくちょく戻ってくる)の横にあり、象の格局がとれる龍穴にある。ちなみに、李登輝も江有庭の作品をちょくちょく買いに来る。
江有庭の家と窯は、元中華民国総統(1988-2000)である李登輝の生まれた実家(今もちょくちょく戻ってくる)の横にあり、象の格局がとれる龍穴にある。ちなみに、李登輝も江有庭の作品をちょくちょく買いに来る。
天目茶碗の魅力は、自然と醸された様々な彩と共に、茶碗の奥底に吸い込まれていきそうな吸引力を伴った美だ。それは、瞑想世界そのものでもある。
とりわけ、天目茶碗は、水を注ぐと茶碗の底にホログラフで作られたような透明な眼球が出来上がるところだ。ちなみに、一年で一つも天目として焼きあがらないこともあるという。まさに、仕上がりは自然に任せるがままなのである。
江有庭は、自分なりに洞察を得た思想の表現としての作品と共にあり、そして、自然の恩恵を授かっている。自然の力が江有庭を代弁者に仕立て、我々がかつて知りえた以上の色彩が江有庭の作品を通して顕われる。そこに、色の有無というものを感じる。

色は、有るのか無いのか?
これだけの色彩を天目茶碗に引き出す彼は、そこに集まった大きな力の自然を授かり、借りて、表現するが、そんな彼自身は、「作品は無為だ」という。つまり、自分という人為を否定しているのだ。
江有亭は、「これらの作品に表れる色彩は、自然の美しさであり、決して自分の人為的な力によるものではない。」と言う。
つまり、作品は彼が作ったものだが、この作品に表れる色は、彼が作りえるものではないということだ。
そのため、一つとして同じ色のものを作ったことが無いし、それは、不可能だという。確かに、ここから迸る一つ一つの色を彼が作ったのならば、彼は、詐欺師だ。この色を作った人の名を我々が知りえるはずが無い。
この色には、何千年にもわたり著作権が無い。
また、表現もできないし、見ていない人に伝える言葉が無い。
つまり、手紙にもかけない。
そのように考えると、我々が持つアイデンティティーというものが如何にいい加減なものか明らかになる。
 我々は、物を指名することはできるが、決して所有することができない。
我々は、物を指名することはできるが、決して所有することができない。
何故なら、人に所有物を伝えるほど、我々は、共通概念を持ち合わせていないのと、同時に、自分に対して物というものを指名するすべは知っているが、漠然とした空間の中に保存されたファイルのようなもので、それを認識するにはいたっていない。
この天目茶碗で示した色について見られる例が顕著だ。
我々は、この天目茶碗を買うことはできるが、所有することはできない。ここで、例を挙げるならば、それは、私がこの色を皆さんに言葉で伝えられないことから明らかだ。
それには、皆さんが私の所有する天目茶碗を知らないし、たとえ知っていたとしても、その色を肉眼で見ながら表現しようとするのに及ばない、つまり、使わなくなった奥底にしまったフォルダーからファイルを取り出し、開くのと同じなのである。
つまり、我々が持ち合わせているものは、共通概念による意思伝達によって、これらの色を互いに、思い出すことができるが、それは、おかしな行為だということだ。
というのも、例えば、この茶碗に関して言うならば、非常に近い意味でのこの茶碗の色彩および形態を表現することはできるが、相手は、それを聞いたときに自分の見聞きした範囲で、それを想像し、なるほど、そういったものをあの人は所有しているのかと思う。
そうしたとき、ここに幾つかの間違いがある。
まず、この詳細な説明を受けても、人は自分が持っている厳密な物の大きさに対する観念さえ、一人として、ぴったり、ミリ単位で共通のものを想像しているとはいえない。
つまり、これらのものを想像することができるが、実際に、認識に至っていると思われるその記憶の中にある観念は、色でさえ、正しく表現できているか定かではないし、大きさでさえ、まちまちである。
そこには、この天目茶碗というものに対して再現性が無いのである。
つまり、この点を考慮するならば、茶碗は持ち主とされる人、そして、持ち主であるが故に、他者自体も、それをこの人の所有物だと思うが、この持ち主も、誰かの所有物とされ、実際にこの茶碗を所有してる人を所有しているとと判断する側の他者も、不思議なことに、これらの所有物を表現するが、そこには、このものに対する食い違いが生じることになる。
両者の記憶のされ方、仕方の違い、そして、記憶されたものを表現するときの表現力の違いなど様々な要素が働き、両者が表現を試みた同じ対象物であるはずのこの一つの茶碗は、既に、二種類の表現力から見直されたもので両者の見解に食い違いがありながら存在するものということになる。
この茶碗という存在は、「認識されていない」ということになり、この両者も自分なりに茶碗を「認識し記憶していると思う」という一つの観念に住んでいるだけで、実際に、物とされる物は、全て、その持ち主が自分が所有しているという観念の中でのみ所有されるのであってその本質が掌握されるわけではない。
人の記憶とは、自分が作り出したおよそ類似しているであろうというコピー、つまり影の投影、幻影に過ぎない。 人は、これらの所有物に対して、「まさか、自分が所有していない、なんて!とんだ、言いがかりだ!」と怒るかもしれない。そして、この人は言うだろう。
人は、これらの所有物に対して、「まさか、自分が所有していない、なんて!とんだ、言いがかりだ!」と怒るかもしれない。そして、この人は言うだろう。
「私は、毎日、この茶碗で、お茶を飲み、時には、その色に見とれ、とにかく毎日接している。そして、それは、私が所有者だから、そのような権利を有し、そのように所有することができる」と考える。
このような見解の相違は、彼自体の言葉で言うならば、この茶碗に「触れられる」ということが彼が、この茶碗の理解者であり、所有者であるという幻想に結びつく。
この茶碗は、物質的なものであり、触れられるだろう。肌身離さず、もって歩くこともできる。しかし、何故、先ほどの言葉で言えば「この持ち主のものとされるこの茶碗を所有してる人と持ち主のものと判断する側の他者も、不思議なことに、これらの所有物を表現するが、そこには、このものに対する食い違いが生じる」のであろうか?
それが、至極単純なものであり、規格化された色・サイズであるならば、両者の表現は、言葉というものの上では一致するだろう。 しかし、この天目茶碗のように、既に色という色だけいうならば、言葉に無い色と組み合わせということになり、両者ともに、共通項である共通概念を有していないため、それぞれが、自分なりの記憶を元に、概念を作成するのである。そして、これは観念とされる。自分では、そうだと思っているという状態の進行形である。
しかし、この天目茶碗のように、既に色という色だけいうならば、言葉に無い色と組み合わせということになり、両者ともに、共通項である共通概念を有していないため、それぞれが、自分なりの記憶を元に、概念を作成するのである。そして、これは観念とされる。自分では、そうだと思っているという状態の進行形である。
そして、人間は、この茶碗の大きさ例えば、直径何ミリだということを知らされていないならば、それぞれが予想し、概念とする。
概念とは、本人の持つ認識力から導き出された予想という段階で、それがおよそ、事実、真実ではない状態の進行形である。
つまり、概念とは、事実、真実とは、違うかもしれない状態を引き受け続ける進行形ならば、概念、予想された上での記憶というのは、事実とは、異なると断言できる。
 物に対する所有者の定義とは、おおよそ「所有者たる自分だけが、触れる権利を有している」ということだが、所有者は、触れられるという、この物に対して、自分なりの記憶を元に、概念を作成しているが、先ほど述べたように、所有物が、所有者にだけそれがその人の所有物として立脚されるならば、それは、我々が認知している範囲での共通概念としても間違った立脚方法であり、所有者は、所有物を有しているか、いないかという段階に際して「他者の判断を必要とする」ということを先に述べておきたい。
物に対する所有者の定義とは、おおよそ「所有者たる自分だけが、触れる権利を有している」ということだが、所有者は、触れられるという、この物に対して、自分なりの記憶を元に、概念を作成しているが、先ほど述べたように、所有物が、所有者にだけそれがその人の所有物として立脚されるならば、それは、我々が認知している範囲での共通概念としても間違った立脚方法であり、所有者は、所有物を有しているか、いないかという段階に際して「他者の判断を必要とする」ということを先に述べておきたい。
たとえば、ある人が、買い物の際、テーブルを指差し、「ここに五キログラムの金がある。お釣りは、要らない。」といって、店を去ったとしよう。
しかし、この金の所有者であった彼は、自分では、そこに金があると信じていたのかもしれないが、もし、他者である店員がそれを見出すことができなかったのならば、それは透明な金とでも言うことになる。
当然、この店員は、怒り、この男を殴り倒し、警察に突き出すだろう。
ここで定義として述べるが、所有物を少有しているか否かは、個による証言だけでは、この所有物の存在は立脚されず、あくまで、この所有物を所有する所有者と他者の判断によって所有物が所有者のものとして有るか無いか認知されるわけだ。
つまり、ここで、矛盾することが、この所有者を通して現れてくることがわかるだろう。
物の所有者は、所有者であると言う自己の立脚に際して、「所有者たる自分だけが、触れる権利を有している」と言うが、この所有物が所有者のものとして認知されるかは、この所有物を所有する所有者と他者の判断によって所有物が所有者のものとして有るか無いか認知されるというのが前提のため、他者の判断が必要になる。
しかし、先ほどから述べているように共通概念として企画化されているもの意外の場合は? 天目茶碗の事例のように、言葉としての単語が無い色と色の組み合わせを持った天目茶碗は、この茶碗の持ち主のものとされるこの茶碗を所有してる人と持ち主のものと判断する側の他者も、不思議なことに、これらの所有物を表現するが、そこには、この物に対する食い違いが生じるのである。
天目茶碗の事例のように、言葉としての単語が無い色と色の組み合わせを持った天目茶碗は、この茶碗の持ち主のものとされるこの茶碗を所有してる人と持ち主のものと判断する側の他者も、不思議なことに、これらの所有物を表現するが、そこには、この物に対する食い違いが生じるのである。
 そして、この食い違いの原因は、今までの手順に従った分析によると、物として至極単純な物、規格化された色・サイズであるならば、所有者と他者の表現は、言葉というものの上では一致するが、この天目茶碗のように、色という色だけいうならば、既に言葉に無い色と組み合わせということになる。
そして、この食い違いの原因は、今までの手順に従った分析によると、物として至極単純な物、規格化された色・サイズであるならば、所有者と他者の表現は、言葉というものの上では一致するが、この天目茶碗のように、色という色だけいうならば、既に言葉に無い色と組み合わせということになる。
 両者ともに、共通項である共通概念を有していないため、それぞれが、自分なりの記憶を元に、概念を作成し、観念とされ、自分では、「そうだと思っている」という状態の進行形が続き、それぞれの予想により、概念化される。
両者ともに、共通項である共通概念を有していないため、それぞれが、自分なりの記憶を元に、概念を作成し、観念とされ、自分では、「そうだと思っている」という状態の進行形が続き、それぞれの予想により、概念化される。
概念とは、本人の持つ認識力から導き出された予想という段階で、それがおよそ、事実、真実ではない状態の進行形である。そして、概念とは、事実、真実とは、違うかもしれない状態を引き受け続ける進行形ならば、概念、つまり予想された上での記憶というのは、事実とは、異なると断言できると私は述べた。
ここで、証明されるのは、所有者がおよそ所有者の側として、自ら所有すると思われるものに対して、「所有者たる自分だけが、触れる権利を有している」と言うこととは、関係なく、物に対する所有者の所有物という立脚が他者による判断によって成り立つと言う定義を与えられたときに、他者の判断は、所有者の判断との見解の一致を見ない物であるならば、所有者が自分のものであると思っていた物は、その人の所有物ではないと言うことになる。
そして、その原因は、所有者と他者の概念の違い、そして、この場合どちら側の概念も等しく、「自分では、そうだと思っているという状態の進行形」に過ぎず、事実とは異なるためである。
これが、社会の中で完全に規格化されたものであるならば、両者の記憶が曖昧な進行形である概念でも、社会の中に用意された絶対と言う基準を元に反射され、規格化されたものならば、共通概念として成立し、他者と所有者の概念に相違は無くなり、物は容易に所有者の物として認知されるだろう。
しかし、社会の中で絶対化されていない規格、とりわけ独自性に富む物、芸術、美術品といったものは、見るものの側で好き勝手に概念化されるため、共通概念が成立しづらく、社会がその物に対する準備を整えるまで、所有者と他者の概念に共通項を見出すのは容易ではない。
こういった点で考えても芸術とは、あくまで、自然に属するものであり、我々が既製化して作成した共通概念と言うベースの上で成り立つものではなく、概念としての成り方自体が異なることがわかる。
そして、ここまでの証明までの持って行き方で、一番強く説明しなくてはならないのは、「概念、つまり予想された上での記憶というのは、事実とは、異なる」と言うことの意味することである。
ここで、思い出してもらいたい。私が一番初めに挙げた仮定。「我々は、物(ここでは、天目茶碗)を所有することはできないが、指名することはできる」と言うのが、私が取り上げた仮定であったが、それは、次のことを意味している。その指名に該当するのが、所有者の所有者たるもっともな台詞「所有者たる自分だけが、触れる権利を有している」である。
これは、他者による立脚と言う点において、ここの図式では却下されたが、それではこのような所有者の持つ感覚とは何か、我々は、無視してはならない。
それは、物と言う物質に接して、人間の感じる感覚、つまり、この場合は、身体からの精神への拘束の現象の一つで、それが漏の加速として現れたときに、記憶となり、身体が物質に接した感覚である触れるという行為が、その存在とともに自動的にも認知すると言うことである。
また、人がこの習慣性を用いて、物に接したときに、物は、完全なる物質と化す。
つまり、物に対する判断は、判断者である我々の側で、精神的か物質的かと勝手に区分けしているだけで、存在としてのものに、物質的、精神的という区分けは無く、己の思考の中で勝手な乖離が始まり、それが既に習慣的とも言える共通概念として、勝手な概念なのにもかかわらず、認識だと思っている点が、間違いなのである。
そして、物に接するに当たって、それを物質的であると「認識していると思っている」と言う状態が間違いなのである。
 まず、我々は、この天目茶碗と接するときに明らかなように文化的に構築された社会が持つ色という言葉の単語が足りずに、表現できないという状態を考えてみてもらいたい。
まず、我々は、この天目茶碗と接するときに明らかなように文化的に構築された社会が持つ色という言葉の単語が足りずに、表現できないという状態を考えてみてもらいたい。
そして、表現できないこととは、概念は、社会が持つ絶対基準と対称にされたとき、違わなければ、事実であると言う点から、これらの色の表現が絶対基準としての社会の中に照らしたとき、持ちえていないということは、既に社会常識で考えても認識にいたるはずがないと言うことになるのである。
何故ならば、先ほど証明したように、共通概念を得られず、自分ではこうだと思っても、他者による判断の一致を見ないならば、少なくとも、社会の中でと言うことならば、それは、事実とはなりえないからである。つまり、「自分では、そうだと思っているという状態の進行形」に過ぎず、事実とは異なるということだ。
認識という定義を人がどのような範疇で用いているかで、異なるのだろうが、少なくともその絶対は、社会の中に共通概念があるか、また、それに照らし合わせ整合性を見出せるかということになり、人は自分の持つ認識というものの大半を既に社会の中にある絶対基準に準拠しきっているのである。
社会学的な説明を加えるならば、社会は、規定をし、概念を事実化、または、法的に、規制的に事実化するが、裏を返せば、人の持つ認識の個性化を認めず、それらは、芸術、もしくは、精神異常といったカテゴリーに追いやり、規制化された認識以外は、事実として認めない、つまり、人間の持つ認識さえ規定しているということになる。
社会の持つ方向性、集合性、民族性、文化性、歴史性、政治的特質、国際関係などといった様々な要因と絡み合っている。
結論的に、人間の持ちえる認識は、既製化されたものであるということだ。
そのため、どういった地域に住んだことがあるかという問題が、どういった認識力を兼ね備えた判断力、思考力を持った人間であるかという国民的性質の違いは、顕著に現れているのである。
そして、世界は作られていると言っても過言ではない。
さて、本日の講義で気に留めてほしいのは、「精神的、肉体的という区別や様々な規範に及ぶカテゴリーの区分けは、用意された共通概念を認知する立場から、認識を社会に依存しきるために生まれた分類であり、単なる社会の中の認識に依存しているに過ぎない」と、言うことである。
つまり、あなたは何一つ自分で勝ち得た認識を持っていないかもしれないという真実であり、ここから作られた世界に閉ざされた自分を見出すことができるだろう。既製品の認識を身に纏い、それらが全てつくられた物であることも知らず、アイデンティティー(自己の存在証明)に変えて、身にまとった認識をさぞ立派なものとして誇りながら生きてゆく。自己の認識にこびりつく様に。
しかし、作られた認識を植えつけられ、作られた世界に生かされている事実に人は真の芸術に出会ったときに気づく。そして、真の芸術を認識できない自己を虚しさと共に見出すのだ。その時、そこから「作られた世界」にある既製品の貧しい認識しか持っていない己を見出すだろう。この天目茶碗が一例である。
皆さんの知っていると思われる世界(作られた世界)の定義も、ほら、こんなにも簡単に揺らいでしまう。
真の芸術家は、既製品になかった新しい認識(芸術)を人間の意識に届ける。だから、当然時代に認められるはずも無いし、誰かに理解してもらうのも不可能なのである。もし、理解者がいるのならば、既存の認識を壊した真理の探求者とも呼べる修道家たちだけだろう。真理の探求者とは、究極の芸術家になりえる可能性を秘めている。
ただし、作られた世界から逃れることができればだが。
*本文は、六年前にMSNチャットで、即興で講義した内容をそのまま掲示しました。
<エッセー集>
エピローグ:「荷物と心の整理」
「空海の文化」
「中国における思想と仏教」
「後期密教における力の顕現」
「神智学協会とインドにおけるユートピア」
「そして、世界は作られている」
「自然への道」
*これらのエッセーは12年前に書かれたものです。まったく加筆、訂正していません。